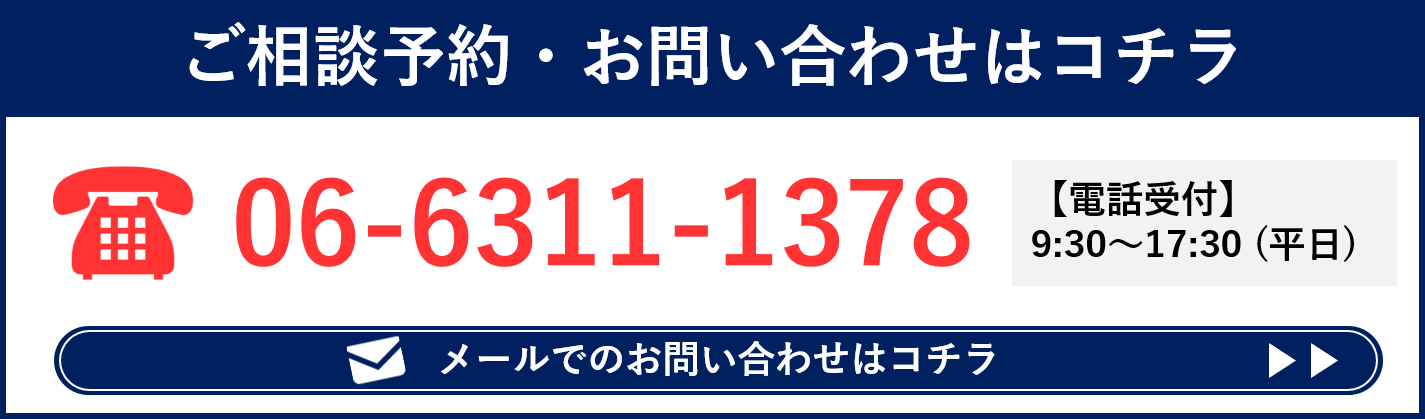はじめに
企業活動において、従業員のパフォーマンスや協調性の低さが職場の秩序に悪い影響を及ぼすことは言うまでもありません。中でも、いわゆる「問題社員」と呼ばれる従業員が現状の職場の秩序を乱し、全体的な業務効率を低下させている場合、その状況を改善するために「配置転換」を検討することは少なくありません。
しかし、配置転換は場当たりにするのではなく慎重に進める必要があります。配置転換が違法と認定されれば、配置転換が無効となるだけではなく、場合によれば企業側が損害賠償責任を負うリスクがあるためです。
本コラムでは、問題社員の配置転換に関する法律上の注意点を解説いたします。
配置転換とは?
配置転換とは、従業員の職務内容、勤務地、勤務体制などを変更する人事上の措置をいいます。典型例としては、営業職から事務職への転換、本社勤務から支社勤務への異動、日勤から夜勤への変更などが挙げられます。
配置転換は、労働契約上の「労働条件」の一部を変更する行為であるため、会社には一定の裁量権(人事権)があります。ただし、その人事権の行使が濫用と評価されると無効・違法と判断されます。例えば、従業員に著しい不利益を与える場合や不当な動機・目的で配置転換を命じた場合には、権限濫用として無効・違法と判断される可能性があります。
配置転換が無効となるケース
配置転換命令が有効となるためには、以下の要件が必要になります。
1.労働契約上、会社に配置転換命令権が与えられていること
2.配置転換命令権の濫用にあたらないこと
まず、「1.労働契約上、会社に配置転換命令権が与えられていること」といえるためには、例えば、就業規則において、「会社は、業務上必要がある場合、従業員に対して就業する場所や従事する業務内容の変更を命ずることがある。」と規定されている場合は、この1の要件を満たします。ただし、もともとの労働契約に「職種限定合意」がある場合は要注意です。就業規則に配転転換命令権の定めがあっても、従業員との間で職種を限定する特別な合意がある場合は、会社に認められる配転命令権はその合意の範囲内に限定されるため、その範囲を超える配転命令権はなく、1の要件に欠けて無効・違法となります。
次に、「2.配置転換命令権の濫用にあたらないこと」について、以下の事情があれば、配置転換命令権が濫用であると評価されると言われています。
① 配置転換命令に業務上の必要性が存在しない場合
② 配置転換命令が不当な動機や目的をもってされた場合
③ 配置転換命令が労働者に著しい不利益を負わせる場合
具体的には、まず①については、社内の労働力の適正配置や、業務効率化、従業員の人材育成、業績悪化時の雇用の維持など、会社の合理的な運営のためといえる程度の理由があれば、配置転換について業務上の必要性がありますが、従業員から質問されたら答えられるように事前に理由を用意しておきましょう。
次に②については、従業員に対する嫌がらせや報復(内部告発への対抗措置など)、懲戒的意図(事実上の制裁)、従業員を退職へ追い込むため等の場合は、不当な動機や目的をもってなされたとして、権利の濫用として無効・違法になります。
最後に、③については、転勤に伴い育児や介護など家族の生活に大きな負担を与える場合や、わざわざ資格や経験を活かせない業務への配置転換を命じて極端にキャリアを損なう措置を行う場合などが「労働者に著しい不利益を負わせる場合」として無効・違法になります。
能力不足を理由とした配置転換の可否
問題社員の中には、業務遂行能力が著しく不足していたり、職場内での協調性に欠けるケースがあります。こうした「能力不足」や「勤務態度の問題」は、配置転換を正当化しうる理由になり得ます。
ただし、単なる成績不振や上司との相性といった曖昧な理由では、上記2の①の「業務上の必要性」は認められませんので、客観的に見て業務上の支障があること、また、その業務に継続して配置することが不適切であることが説明できるように、これまでの事実関係や裏付けの資料などの整理が必要になります。
加えて、配置転換後の職務内容が、従業員の経験・能力と大きく乖離していると、上記1で述べた「職種限定合意」として合意の範囲外と認定されて上記1が欠けて配置転換が無効・違法とされます。また、上記1の要件は満たしても、上記2の③「労働者に著しい不利益を負わせる場合」として権限濫用として無効・違法とされるリスクもあります。
違法な配置転換を行った場合のリスク
配置転換が違法であると認定された場合、企業側には以下のような法的・経営的なリスクが発生します。
• 配置転換命令の無効確認請求
• 配置転換の違法性を理由とする損害賠償請求(精神的損害、給与差額など)
• 労働審判や訴訟対応の負担増
• 企業イメージの悪化・SNS炎上のリスク
• 従業員全体への信頼低下と士気低下
特に近年は労働者側の権利意識が高まっており、SNSや口コミサイトなどで炎上や低評価を受けて、求人活動が困難になるなど、企業経営に深刻な影響を及ぼす事例も見受けられます。
違法な配置転換とならないための対策
適法に配置転換を行うには、以下のような手順を踏むことが重要です。
1. 就業規則の周知と労働契約書の点検
配置転換権の根拠となる条文を明記し、普段から従業員への周知を徹底します。
また、実際に配置転換をする際には、「職務限定合意」が明示または黙示的に認定されないか、労働契約書を点検する必要があります。
2. 配置転換の理由の明確化と記録化
能力不足や職場秩序維持の必要性を客観的に説明できる資料・記録を用意します。
その上で、要件2の①の「業務上の必要性」が丁寧に説明できるようにしましょう。
3. 事前の面談実施(不利益への配慮を実施するため)
要件2の③の「配置転換命令が労働者に著しい不利益」とならないようにするためには、配置転換を言い渡す前に、配置転換の内示とその際の不利益を聴取・意見交換するために、当該従業員と面談を実施すべきです。
その際に、家族状況、通勤時間の変化、生活環境への影響等を十分に聞き取り、従業員と意見交換し、その面談を踏まえたうえで、不利益への配慮をできるだけ実施できるように準備し、また当該従業員にそのような配慮を行うことを伝えて安心させる必要があります。
4. 本人への説明と同意の取得(可能な範囲で)
このように従業員と面談を重ねて、不利益があっても企業側でできることを伝えて安心させてください。誠実な対話を心がけることで後の紛争を予防できます。
問題社員の雇用維持のための配転であっても、一方的に配転命令を出すのではなく、事情を丁寧に説明し同意獲得に向けた努力が必要となります。
5.配置転換命令の通知
最終的に、同意が獲得できない場合は、配置転換命令の通知書を一方的に交付することになります。なお、4で丁寧に説明し面談を重ねた努力により、配置転換が有効・適法となりやすくなります。
当事務所がサポートできること
当事務所では、問題社員への対応や配置転換を巡る諸問題について、以下のような法的サポートを行っております。
• 就業規則の整備・見直し
• 配置転換や懲戒処分に関する法的アドバイス
• 労働審判・訴訟への代理対応
• 配置転換実施に向けた書面作成・記録整備
• 社内研修やセミナーの開催(人事労務担当者向け)
配置転換は丁寧かつ慎重な事前準備、有効要件を満たす説明内容など、過去の裁判例に照らした専門的知識・経験が不可欠です。当事務所では、長年にわたり企業側労働問題を扱ってきた経験や専門的知識に基づき、配置転換が労働トラブルに発展しないように、全力でサポートさせていただきます。
配置転換に関してお悩みの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。