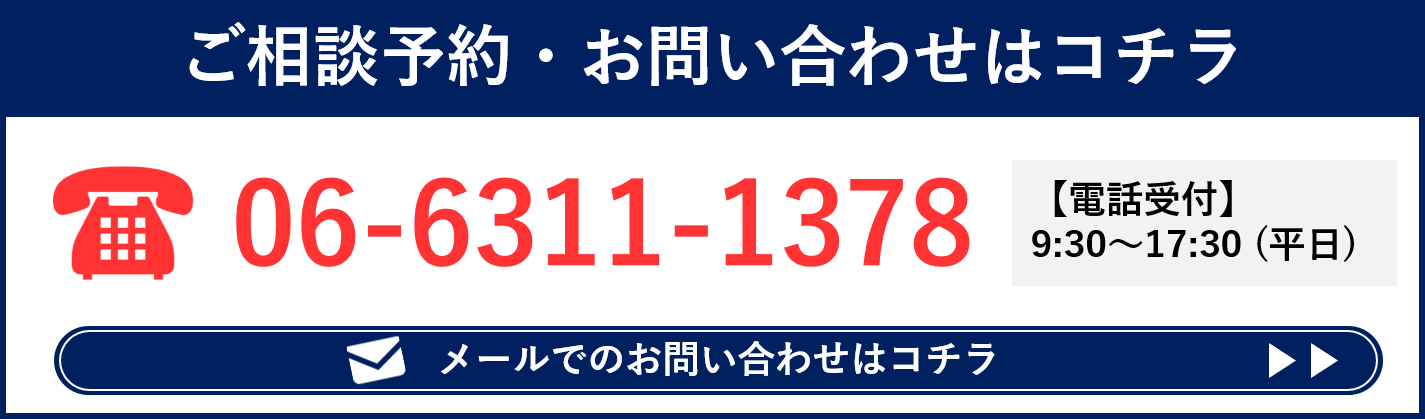企業経営において、著しい問題行動を繰り返す問題社員への対応は避けて通れません。
本コラムでは、問題社員の解雇に至るまでの法的留意点と実務対応のポイントを分かりやすく解説します。
令和型の問題社員の特徴・傾向
令和特有の問題社員の特徴・傾向は以下のとおりです。
SNS過剰発信型の問題社員(社内告発系インフルエンサー)
上司や同僚の発言、社内会議の内容などを批判的に中傷してSNSに投稿する。
特性やメンタル不調をタテにする問題社員
病気、障害、特性を理由に、業務の拒否、指導教育の拒否、過剰な配慮を要求する。他方で診断書などの提出はなく本当に病気か不明。
ハラスメント・ハラスメント型の問題社員
上司の正当な指導教育を「パワハラ」に当たると主張して指導に従わず過剰に被害を訴え続けて他者の時間を奪う。
指示待ち型の問題社員(自ら動かず、指示がないと行動できないタイプ)
与えられた業務は正確にこなすものの、自分から動こうとせず主体性・自発性が欠如している。自分から動くことが「損」であると考えているタイプもいる。
協調性欠如型の問題社員
チームでの共同作業に非協力的で、指示もやんわりと無視し、無自覚でチームワークを乱し、孤立や対立を繰り返す。
反抗的態度型の問題社員
上司や同僚に対して、常に反抗して対立的な言動を取るタイプ。中には、子分を引き連れて社内に反対勢力を作るタイプもいる。
離席常習型の問題社員
トイレや体調不良を理由に、不合理な頻度・時間数離席を繰り返し、離籍中何をしているか不明。
<令和型の問題社員の特徴・傾向>
1.権利意識は強いが義務意識(帰属意識)が乏しい。
労働法やSNS情報で知識はあるが、業務責任や職場貢献には無関心。
2.精神的な耐性が低く、注意指導を「ハラスメント」と捉えやすい。
指導への拒否反応が強く、メンタル不調や被害意識に転化しやすい。
3.「個の自由」や「自分らしさ」を過度に優先し、組織規律と衝突しやすい。
就業規則やチームルールよりも、自分の価値観を優先。
4.業務の「見える化」や「成果の納得感」がなければ不満を表明しやすい。
上司の主観評価や曖昧な評価軸に強く反発。説明責任を求める傾向が強い。
インターネットやSNSの発達により、あらゆる情報の入手が容易になった結果、権利意識が高まり、自分の価値観を優先する風潮があり、そのこと自体は良い側面もありますが、他方で情報の独り歩きや既存の価値観への過剰な拒否反応などにより、職場での問題行動に繋がっているように思えます。
それでは、このような問題社員を解雇することはできるのでしょうか。
解雇における基礎知識
解雇には、労働契約法第16条による厳しい規制が適用されます。具体的には、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法第16条)。
解雇が認められるための要件
上述のとおり、解雇が有効とされるための要件は、解雇権の濫用とされないだけの①合理的な理由と②社会的相当性の2点を充足しなければなりません。解雇は非常に厳しい処分となることからも、①合理的な理由と、②社会的相当性の有無を調査・確認し、慎重に検討しなければ、解雇は無効となります。
不当解雇と見なされる可能性があるケース
解雇の有効要件である①合理的な理由が認められない場合とは、例えば、問題の程度が軽微な場合、業務能力の不足が客観的に証明されていない場合、遅刻や同僚との人間関係等、勤務態度不良に関して改善の機会が与えられていない場合などが挙げられます。
また、企業はいったん雇用した以上その雇用を維持する責任があるため、解雇の場面でも雇用を維持する責任、つまり解雇を回避するための努力(解雇回避努力義務)を尽くさなければ、②社会的相当性が認められません。例えば、解雇という処分が、問題点に対して重すぎるような場合、長期勤続者に対する突発的な解雇等が挙げられます。
このように、上記①②の要件をみたさない限り、例え問題社員であっても、不当解雇であるとして、解雇が無効と判断されることがあります。
解雇に踏み切る前に企業が実施しておくべきこと
注意・指導
解雇回避努力義務の一環として、問題社員であれば適切な指導・教育・研修により問題点を改善する機会を与えなければなりません。その機会を与えたにもかかわらず、改善の見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、研修、トレーニング、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)などにより、問題点を改善する機会を与えることが必要です。
また、月に1回程度の定期的な面談で改善状況を確認し、改善点を評価するとともに、未達成部分には指導助言を行います。
このような指導・教育・研修を面談記録や指導書などの書面に落とし込み、その書面を従業員に共有しながら実施することで、従業員が課題を適切に理解し改善に取り組むことができます。一方で、企業側も合理的な指導を行った証拠を残せるため、最終的に解雇が必要となる場合の正当性を補強することができます。記録には日付、内容、参加者の署名などを記載しましょう。
配置転換
従業員の問題点が改善されない場合、解雇する前にまず、配置転換を検討しましょう。
配置転換を行う際には、その理由を丁寧に説明し、従業員の意向を確認することが重要です。納得感を得るために面談や書面で異動の目的やメリットを伝えます。異動後も適切なフォローを行い、研修や指導を通じて新しい業務に適応できるようにサポートすることも説明して安心してもらう必要があります。
懲戒処分
問題社員に対しては、直ちに解雇するのではなく、就業規則に基づき段階的な懲戒処分を検討することが重要です。懲戒にはけん責・減給・出勤停止・諭旨解雇・懲戒解雇などがあり、違反行為の内容や程度に応じて相当な処分を選ぶ必要があります。
また、事前の事情聴取や証拠の確保、公正な手続の実施も欠かせません。処分が重すぎたり、手続に瑕疵があると、無効とされるリスクございますので、ご注意ください。
退職勧奨
退職勧奨については、最近よく耳にすることも多いかと思われます。退職勧奨とは、社員の同意を得て自主的な退職を促すものであり、あくまで任意の話し合いによる合意が前提となります。
もっとも、会社側が問題社員に対し、退職に関する威圧的な言動や繰り返しの強要があった場合には、不当な退職強要とみなされる恐れがあり、違法と判断される可能性もございます。話し合いの際の録音や記録の保存等、会社側の適切な対応、が重要となります。
解雇
上記ご対応の後、最終手段として検討されるのが「解雇」となります。
解雇を行う前に、まずは、過去の裁判例に照らし、解雇が有効であると認められるか否かの見通しを立てる必要があります。これまでに行った指導や配置転換、懲戒処分の経緯を記録し、合理的な改善期間を設けたことを証明する必要がありますので、この点も最終確認しましょう。
また、「解雇」がやむを得ない状況であったとしても、いきなり解雇を通知するのではなく、まずは上記退職勧奨により、合意による円満退職を目指すことをお勧めします。解雇の場合、解雇法理による厳格な規制や、解雇予告手当金などの規制がありますが、上記退職勧奨による合意退職の場合、これらの規制は及ばず、不当解雇リスクを回避することができます。
問題社員の解雇を検討されている企業に対して弊所がサポートできること
弁護士法人ブレイスは、普段から多数の労働問題に対応してきた実績があります。問題社員の解雇を検討されている場合は、是非ともご相談ください。労働トラブルの回避にお役に立てます。
問題社員への対応に関するアドバイス
当事務所は、問題社員の種類とそれに応じた適切対応に詳しい弁護士が所属しており、過去の経験やノウハウ、これまで蓄積された判例などの知識により、適切なアドバイスができます。
問題社員への対応は、従業員の問題行動の調査、指導教育、懲戒処分のタイミングやその内容程度の検証など、高度な専門的知識・経験を要する分野です。問題社員への対応は、厳格な解雇法理との関係でも慎重かつ地道な対応が必要となります。問題社員対応に詳しい当事務所の弁護士が問題社員の問題行動を細かく聞取りさせていただいた上で、適切な指導教育の方法、改善の見込みの判断、改善が困難である場合の最後の手段として退職勧奨か解雇かの選択など、現状で採ることができる対応と解決に向けたスケジュール管理を提案いたします。
体制構築に向けた書面の整備
問題社員による問題行動は、社内に必要なルールが整備されていないことが原因であることがほとんどです。問題行為に対応できるルールが存在しない場合には、これに対応できるルールの整備を行う必要があります。
当事務所では一般的に必要と思われるルールの策定を支援させていただくとともに、個別の企業様の状況に合わせて必要なルールの整備をご提案させていただきます。その際に必要な書面も、当事務所は、これまでの経験・実績に基づき、多数用意させていただけますので、書面作成や点検による労力や手間暇を大幅に削減できます。
退職勧奨・解雇等の有事対応へのサポート
退職勧奨や解雇などで問題が発生した場合、労働法に精通した弁護士が適切な初期対応をアドバイスさせていただくとともに、労働者との交渉や訴訟の対応など代わりに行います。当事務所は、企業側に立って、退職・解雇を巡る交渉や裁判を数多くこなしてきた実績があります。労働訴訟や労働審判になると、どのくらいの期間を要し、どの程度の金銭支払いを要するかなど、その経験や実績に基づいた相場観を示すことができます。
そのため、退職・解雇を巡るトラブルが法的紛争に発展した場合も、当事務所はその経験・実績により、適切なタイミングと金額で早期解決を実現することができます。間違えても、企業様に無謀な戦いをさせて、高額な金銭支払いと復職という最悪な結果にならないように交渉いたします。また、労働訴訟や労働審判に発展しても、当事務所の弁護士が企業様に代わって、適切かつ効果的な立証活動により手続を有利に進めるとともに、依頼者を手続の負担から解放することができます。
顧問契約による相談体制の構築
問題社員が社内で好き勝手に振る舞っている企業様は、そもそも、その企業様の労務管理において根本的な問題やリスクが潜んでいる可能性があります。仮に、ある問題社員が退職したとしても、その退職は対症療法に過ぎず、根本治療がなされないまま、再度同様の問題社員が現れることことがあります。労務管理のずさんが原因で、本来真面目な従業員が問題社員へと変化していくこともあります。そのような問題社員の出現を繰り返す許す企業様も実例として見てきました。
当事務所では、顧問契約や労務コンサルティングにより、労務管理における根本的な問題やリスクを解消することができます。このような根本治療により問題を根本的に解決できれば、問題社員が問題行動を行うこと自体を防止し、行動を改善して問題社員でなくなるか、もしくは自ら退職してミスマッチ解消されるか、いずれにせよ良い結果をもたらします。企業様が望む組織体制の強化を図るためには問題社員対策は不可欠です。
同じ労働問題に対して、事前法務・日常管理的な業務を行う社労士と、事後法務・危機対応的な業務を行う弁護士とで、事案の捉え方や解決の視点が異なることがあります。また、ある法改正でも、社労士と弁護士とで視点が異なるため、法改正情報の着眼点や重視するポイントが異なります。時として、顧問弁護士と顧問社労士の見解が異なり、どちらの見解に従えばよいか混乱している企業様もいます。
当事務所は、顧問契約や労務コンサルティングにおいても、弁護士・社労士の両視点を統合した最適解や重要情報を提示しております。
問題社員への対応に関するご相談は労務問題に精通した弁護士と社労士が在席している当事務所にお任せ下さい。
顧問契約を頂いている企業様に対しては、日頃から労働法に精通した弁護士に気軽に相談できる体制を構築させていただきます。問題社員対応は、解雇などの問題に発展してからご相談いただくことが多いですが、既に手遅れであるケースが散見されます。問題社員への対応は日頃から適切なステップを踏むことが非常に重要ですから、日頃からご相談いただくことは非常に重要といえます。