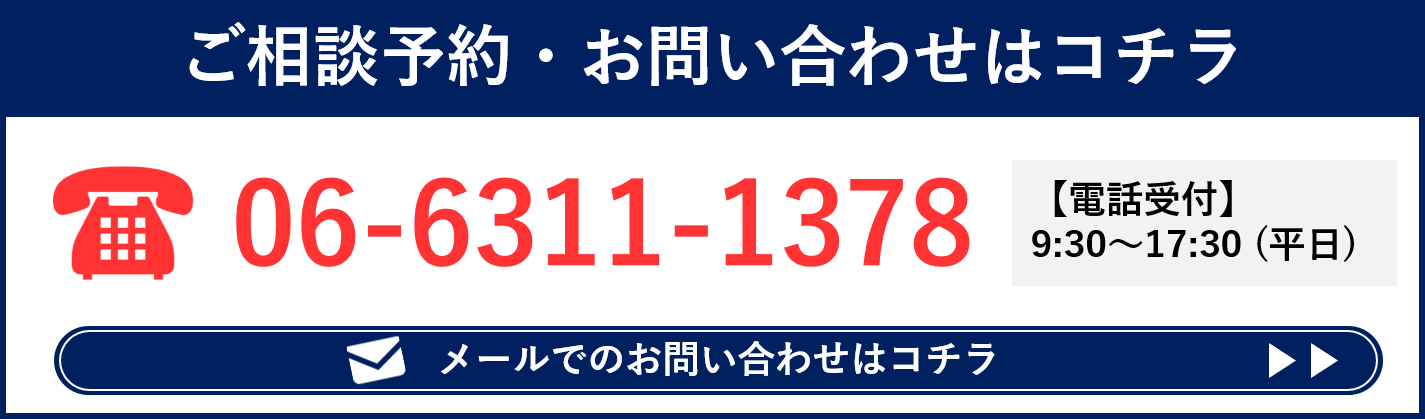「毎朝ギリギリに出社し、あいさつもしない」
「自分の独自のやり方にこだわり、何度も同じミスを繰り返す」
「同僚に攻撃的な言動を繰り返して協調せず孤立している」
このような社員を「問題社員」として認識しながらも、対応を後回しにしていませんか?
中小企業の経営者や労務担当者から、こうした問題社員に関する相談は非常に多く寄せられます。このような問題社員の対応は非常に手間暇がかかり、かつ気を遣うことも多く、ついつい放置したくなります。また、対応を誤ればトラブルに発展するおそれがあるため、「下手に刺激しないほうがよいのでは」と判断して何もせずに放置してしまうケースも見られます。しかし、問題社員の放置は、会社全体に深刻な悪影響をもたらすことがあります。
本コラムでは、問題社員を放置したことによって生じる具体的なリスクを、ある中小企業で実際に起こったエピソードを交えて解説し、適切な対応策を提案します。
問題社員を放置するリスク
職場環境の悪化
問題社員の言動が改善されないままだと、周囲の社員の不満やストレスが蓄積します。「あの人は何をしても許される」という印象が職場に広がれば、組織全体の規律やモラルが崩壊しかねません。さらに、優秀な社員の離職を招くことすらあります。
大阪府内のある製造販売業(従業員200名)では、協調性に欠ける問題社員が同僚に対して常に攻撃的なメールやLINEを送り続け、また独自のこだわりや主張を上司や同僚にぶつけて周囲の者の時間を奪うことがありました。会社は2年以上適切な対応をできないまま放置していましたが、その間職場環境は悪化し、モチベーションも低下し、多くの社員が離職していきました。
生産性の低下
問題社員が適切に業務をこなさない場合、そのしわ寄せは他の社員に及びます。業務分担の不均衡や再発するミスのリカバリー対応により、組織全体の効率が落ちてしまいます。結果として顧客満足度の低下にもつながり、企業の信用に傷がつくこともあります。
大阪府内にある介護施設(従業員50名)では、正当な理由のない業務拒否や、作業の手抜き、業務時間中の睡眠が目立っていました。上司も何度か注意したものの、本人は「自分はちゃんとやっている」と反論し、改善の見込みは見られませんでした。人手不足もあり、会社は処分することなく、そのまま放置していましたが、その間利用者からのクレームが相次ぎ、他の社員はそのリカバリー対応に追われて本来すべき業務ができず、他の社員のミスまで誘発されている状況でした。
金銭的リスクの増加
ミスによる損害や顧客からのクレーム対応にかかるコストは無視できません。
よくあるケースは、問題社員が自動車の操作ミスを繰り返して何度も修理費用を発生させたり、不適切な言動でクレームを発生させて上司が何度も謝罪と説明を繰り返したりするなどです。クレーム対応により数時間奪われれば、その分人件費という損失が発生していることを意識しなければなりません。
さらに、問題社員がハラスメントなどの不適切な言動を繰り返して、その結果他の社員が「パワハラを受けて、うつ病になった」「会社はパワハラを放置した安全配慮義務違反がある」と主張されれば、最悪の場合、数百万円、数千万円の損害賠償に応じなければなりません。
業務を一切与えないことによるパワハラ認定
問題社員に困り果てた結果、「業務を与えない」という対応を選ぶ会社もあります。しかし、これは大変危険な対応です。
過去の裁判例(神戸地判平成6年11月4日)では、従業員が配置転換を拒否したことをきっかけに、上司が「今日から仕事はすべて別の従業員にやってもらう」と告げ、仕事を与えなかったこと等が違法であるとして、会社に慰謝料60万円の支払いを命じています。
このように、業務から完全に排除する措置は、本人の名誉や人格権を侵害するものとして違法とされる可能性があるのです。
問題社員を放置せず対処する際のポイント
では、問題社員にはどのように対応すべきなのでしょうか。以下のような段階的な対応が有効です。
注意・指導の実施
まずは具体的な問題行動について、放置せずに、客観的な事実に基づいて注意・指導を行います。この際、単なる口頭注意だけでなく、注意書や指導記録を残すことが重要です。将来的に懲戒処分等を検討する際の証拠となります。また、解雇回避努力義務の一環として、問題社員であれば適切な指導・教育・研修により問題点を改善する機会を与えなければなりません。その機会を与えたにもかかわらず、改善の見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、研修、トレーニング、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)などにより、問題点を改善する機会を与えることが必要です。
面談を重ね、経過観察を行う
指導の後も状況の改善が見られない場合には、継続的に面談を実施し、状況を観察します。本人の意識や勤務態度の変化、改善の意欲の有無を確認し、記録を取りましょう。月に1回程度の定期的な面談で改善状況を確認し、改善点を評価するとともに、未達成部分には指導助言を行います。
これまでの指導・教育・研修を面談記録や指導書などの書面に落とし込み、その書面を従業員に共有しながら実施することで、従業員が課題を適切に理解し改善に取り組むことができます。
配置転換や軽微な懲戒処分
一定の改善が見込めない場合は、職場環境を変える目的での配置転換や、譴責・始末書提出といった軽微な懲戒処分を検討します。ただし、これらの措置を講じる際には、就業規則に則った適正な手続きが必要です。
配置転換を行う際には、その理由を丁寧に説明し、従業員の意向を確認することが重要です。納得感を得るために面談や書面で異動の目的やメリットを伝えます。異動後も適切なフォローを行い、研修や指導を通じて新しい業務に適応できるようにサポートすることも説明して安心してもらう必要があります。
また、問題社員に対しては、直ちに解雇や重い懲戒処分をするのではなく、就業規則に基づき段階的な懲戒処分を検討することが重要です。軽微な懲戒処分として、まずは戒告やけん責、減給処分などから進めてください。それでも改善しない場合は、出勤停止・諭旨解雇・懲戒解雇など重い処分へと進んでください。いずれにせよ、事前の事情聴取や証拠の確保、公正な手続の実施も欠かせません。処分が重すぎたり、手続に瑕疵があると、無効とされるリスクございますので、ご注意ください。
退職勧奨や重い懲戒処分の検討
最終的に、状況が改善されず、業務遂行に重大な支障が出ている場合には、退職勧奨や重い懲戒処分の実施を検討することもやむを得ません。
退職勧奨については、最近よく耳にすることも多いかと思われます。退職勧奨とは、社員の同意を得て自主的な退職を促すものであり、あくまで任意の話し合いによる合意が前提となります。
もっとも、会社側が問題社員に対し、退職に関する威圧的な言動や繰り返しの強要があった場合には、不当な退職強要とみなされる恐れがあり、違法と判断される可能性もございます。話し合いの際の録音や記録の保存等、会社側の適切な対応が重要となります。
退職勧奨に応じない場合、普通解雇ないし懲戒解雇を検討することになります。これらの解雇を行う前に、まずは、過去の裁判例に照らし、解雇が有効であると認められるか否かの見通しを立てる必要があります。これまでに行った指導や配置転換、懲戒処分の経緯を記録し、合理的な改善期間を設けたことを証明する必要がありますので、この点も最終確認しましょう。
いずれにせよ、普通解雇ないし懲戒解雇を行うには、十分な証拠と厳格な手続きが求められますので、必ず専門家の助言を受けるようにしましょう。
問題社員への対応でお困りなら当事務所まで
問題社員の存在は、企業経営にとって無視できないリスクをはらんでいます。「指導するのが面倒」「波風を立てたくない」といった気持ちは理解できますが、対応を放置することの方がはるかに大きな代償を生むこともあるのです。
当事務所では、問題社員に関するあらゆる段階でのサポートを提供しております。注意・指導文書の作成、面談への同席、就業規則の整備、懲戒処分の助言まで、一貫して対応が可能です。現場の実情に即した、現実的かつ法的に適切な対応をご提案いたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。