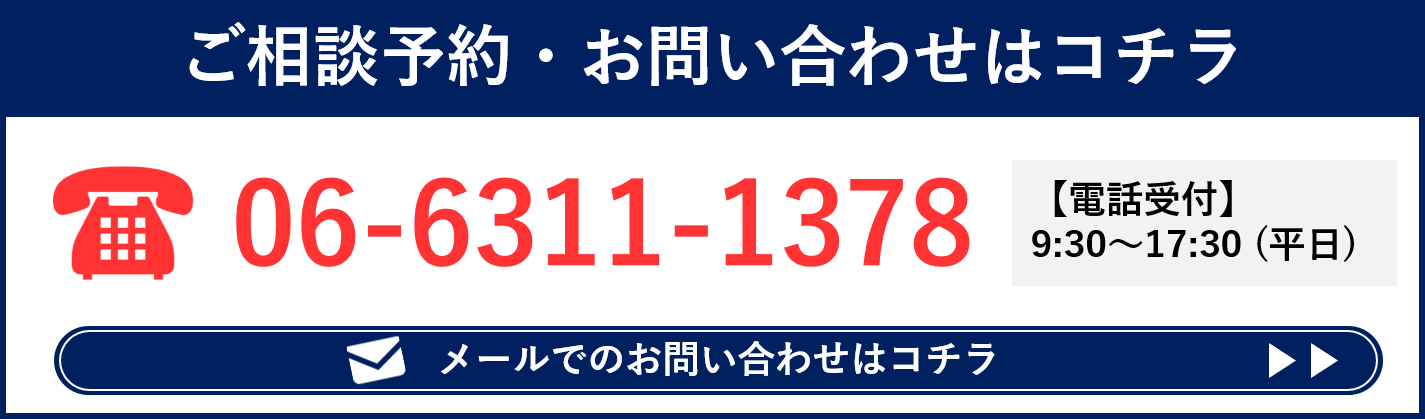新しく従業員を採用する際、多くの企業では「試用期間」を設けています。この期間は、実際の業務を通じてその人材が自社に適しているかを見極める大切な機会です。
しかし、「試用期間だから、いつでも自由に解雇できる」と誤解されているケースも少なくありません。実際には、試用期間中であっても労働契約は成立しており、解雇にあたっては法律上の厳格なルールが適用されます。不適切な解雇は、後に労働トラブルへと発展し、企業側にとって大きなリスクとなる可能性があります。
本コラムでは、試用期間中の解雇がどのような場合に問題となるのか、企業が注意すべき法的ポイントや裁判例を交えて、労働問題に精通した弁護士がわかりやすく解説します。
-
試用期間に関する基礎知識
試用期間とは?
試用期間は、労働契約が始まってから一定期間、使用者と従業員がお互いに相手方の適性や適格性を評価するための期間です。通常は労働契約の一部であり、試用期間中は労働条件が一部変更されることがあります。
試用期間は何か月にすればよいか?
労働基準法において、試用期間の長さに特別な制限はありません。
しかし、合理的な期間であることが期待され、一般的には3か月が最も多く、1~6か月にわたるのが大多数です。合理的理由や必要性がなく、あまりにも長期に試用期間に留めおく場合は公序良俗違反として無効になることもあり得ますので要注意です。業種・業態にもよりますが、1年以上の試用期間は要注意です。
-
パターン別で知っておくべき試用期間設定のポイント
本採用の拒否(試用期間中の解雇)は自由にできるか?
本採用の拒否(試用期間中の解雇)は、そう簡単には認められません。
確かに、このような試用期間中の労働契約が本採用後の労働契約とは別個の契約関係ですと、本採用の拒否も自由に認められそうです。
しかし、過去の判例では、試用期間中と本採用後の契約を同一の労働契約と解釈し、本採用の拒否に制限を加えています。そして、試用期間中は、試用期間独自の解約権がついていて、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められているとされています。このような考え方に基づいた、試用期間中の労働契約は「解約権留保付労働契約」と言われております。
このように、試用期間後の本採用の拒否は、留保された解約権の行使ということになります。
そして、過去の判例(三菱樹脂事件、最大判昭48.12.12)は、試用期間後の本採用の拒否(留保された解約権の行使)について、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められていると言いながら、以下のような厳しい条件を設けています。
「留保解約権の行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」
「採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合にのみ許される」
「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」という表現は、通常の解雇と変わらぬ厳しい制限であり、実務的にも試用期間後の本採用の拒否が通常の解雇より緩やかであるとは感じません。
試用期間後の本採用の拒否は、通常の解雇と同程度にハードルが高く、そう簡単には認められないと考えるべきでしょう。
試用期間を延長することができるか?
業務遂行能力が不十分である従業員については、直ちに本採用ができず、試用期間を延長して吟味したい場合もあります。このように、試用期間経過前に試用期間を延長されることはできないでしょうか。
試用期間の延長は、就業規則などで延長の可能性およびその事由、期間などが明定されていないかぎり原則として認められません。試用期間は労働者にとって不安定な地位であり、その不安定な地位・不利益を労働者に一方的に負担させることはできないからです。過去の裁判例(⼤阪読売新聞事件、⼤阪地判昭42・1・27)も延⻑の根拠規定のあった事例ですが、延⻑には合理的な理由と、かつその理由と期間を明⽰した告知を要するとしたと判断したものがあることにご留意ください。
延長規定がなくても、労働者本人の同意さえあれば試用期間の延長は可能かというと、労働契約法第12条の「最低基準効」との関係で問題となります。就業規則の基準に達しない労働条件は本人の同意があっても無効となりますが(労働契約法第12条)、就業規則に延長規定がない以上、本人の同意があっても延長が難しくなるのです。
裁判例(東京地判令2・9・28)でも、労働者本人の同意のみでの延長が有効となるのは、以下の①~④のすべても満たす場合に限られるとしています。
① 解約権⾏使を検討すべき程度の問題があるとの判断に⾄ったものの労働者の利益のため更に調査を尽くして職務能⼒や適格性を⾒出すことができるかを⾒極める必要がある場合等のやむを得ない事情があると認められる場合に、
② そのような調査を尽くす⽬的から、
③ 労働者の同意を得た上で
④ 必要最⼩限度の期間を設定して試⽤期間を延⻑しても就業規則の最低基準効に反しない。
やむを得ない事情、調査を尽くす⽬的、必要最⼩限度の期間について認められない場合、労働者の同意を得たとしても就業規則の最低基準効に反し、延⻑は無効になると判断されています。
延⻑規定の有無にかかわらず、延⻑に際しては、早めに労働者本⼈と⾯談をして、勤務態度、能⼒などの問題点を書面などで指摘したうえで、改善⽬標を⽰すなどの指導をしましょう。
また、延⻑期間中も、⼗分フォローして注意・指導をする必要があります。このままでは本採⽤はできないとの説明も丁寧にすべきです。
-
試用期間中の解雇に関するトラブル
解雇が認められるケースの例
試用期間中の解雇が認められるケースとしては、以下が挙げられます。
- 出勤率不良や無断欠勤がある場合
- 勤務態度が不良で上司から注意を受けても改善されない場合
- 教育や指導をしたにもかかわらず、一定水準に達しない場合
- 協調性を欠くなど社員としての適格性がない場合
- 重大な経歴詐称がある場合など
また、中途採用の場合には、特定の職位・職種や専門性、キャリアなどを基にした一定の職務遂行能力があることを前提に採用されるため、解約権行使の可否は、労働契約上求められる一定の職務遂行能力を基準に判断される傾向にあります(G社事件・東京地判平31.2.25など)。
ただし、求められる職務遂行能力の内容・程度などを労働契約上、特定することが重要ですので、労働契約書、誓約書、面談記録、その他の書面により、どのような能力を求めて採用したか明らかにしておく必要があります。
注意が必要なケースの例
過去の裁判例では、「新卒採用」は「中途採用」に比べて、よりハードルが高いため注意が必要です。また、「中途採用」でも「未経験者歓迎」などと謳って募集をかけた場合も要注意です。
新卒採用の場合、入社後、OJTなどの教育訓練を通じて人材の育成・活用を図ることが当然の前提とされています。新卒採用は、そもそも能力が低く一定の教育訓練を前提として採用している以上、簡単に解約権の行使を認めるべきでないのです。
裁判例も、新卒採用者の解約権の行使については極めて慎重です。技術職に求められる技能、資質が明確である場合には新規学卒でも留保解約権の行使が認められた例はありますが(日本基礎技術事件・大阪高判平24.2.10)、一般的には留保解約権を否定するものが多数です。
試用期間中の解約権行使における注意点
試用期間中の解約権行使(本採用拒否)が通常の解雇と同程度にハードルが高く、そう簡単には認められないものですので、通常の解雇と同様、手続も慎重に行うべきです。
基本的にプロセスは以下のとおりです。
①指導教育
普段から注意指導を丁寧に行いましょう。必要に応じて、労働者本⼈と⾯談をして、勤務態度、能⼒などの問題点を書面等により指摘したうえで、改善⽬標を⽰すなどの指導をしましょう。
直前になって本採用拒否をするとトラブルに発展する原因となりますので、状況に応じて早めに、面談等においてこのままでは本採⽤はできない旨の説明もすべきです。
②試用期間延⻑の検討
当初の試用期間内では目標に達していないが、注意指導次第では改善目標に達する可能性があり、労働者本人も強く希望する場合は、試用期間の延長も検討しましょう。
ただし、試用期間の延長は労働者本人に負担を与えることになりますので、延長規定の有無を確認するほか、合理的な理由もなく安易に行うことは避けましょう。また、延⻑に際しては、早めに労働者本⼈と⾯談をすることや延⻑期間中も⼗分フォローして注意・指導をする必要があることはすでにのべてとおりです。
③退職勧奨
勤務態度、能⼒などの問題点を指摘し改善⽬標を⽰すなどの指導をしても、何ら効果がなく、改善の見込みがない場合は、いきなり本採用拒否するのではなく、退職勧奨を行うことがお勧めです。
解約権行使(本採用拒否)が通常の解雇と同程度にハードルが高いのですが、退職勧奨により退職の合意が成立した場合は、そのようなハードルを越える必要がなく、解雇リスクを回避することができます。退職勧奨が成功するかどうかは、それまでに丁寧な指導教育、勤務態度、能⼒などの問題点の説明が十分に尽くされているか否かにかかわります。
もっとも、本人が拒否しているにもかかわらずしつこく退職勧奨をすると、その行為が違法性を有し損害賠償責任を負う事態になりかねませんので、退職勧奨の態様や説得の言動・頻度は慎重に検討する必要があります。
④解雇の通知(解約権行使)
指導教育効果がなく、改善の見込みがない場合で、かつ退職勧奨にも応じない場合は、いよいよ解約権の行使(本採用拒否)を検討することになります。
試用期間中の労働契約が「解約権留保付労働契約」であるため、試用期間経過前に解約権を行使しないと自動的に解約権の留保のない通常の労働契約となりますので、経過前に解約権行使の通知書を交付・送付する必要があります。
なお、試用期間中の場合、就労開始から14日以内であれば解雇予告手当は不要ですが、14日を超えて働いている場合は通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要となります(労基法21条4号)。試用期間の残日数が30日未満でも同様ですのでご注意ください。
また、試用期間であっても、労働者から求められれば、会社は、解雇理由証明書を交付する必要があります(労基法22条)。
-
労働問題について弁護士が関与する重要性
高度な知識・経験に基づく労務環境の整備
試用期間中の解雇については通常の解雇と同程度の高度な法律知識、慎重な対応が求められています。雇用契約書の明確な記載(期待する能力の明記など)や指導教育内容の整備、評価基準の適正な設定、従業員とのコミュニケーションが試用期間におけるトラブルの予防に繋がりますが、いずれも弁護士による高度な法律知識、経験が必要となります。
過去判例に基づく対処方法の助言
試用期間中の解雇を踏み切るにしても、それが過去の判例上有効か否か、有効となるためにはどのような施策が必要かなど、労働判例の知識が不可欠になります。
弁護士は過去の判例に基づいて、試用期間中の解雇などについて適切なアドバイスや解決策を提供できます。これにより、試用期間中の解雇に関する法的なリスクを最小限に抑えることができます。
トラブル発展時の迅速な対応
万が一トラブルが発展した場合、さらに労働者側から弁護士が介入したり裁判所から訴状などが届いた場合、労働トラブルに強い弁護士がいれば、直ちに素早い対応が可能となります。法的な手続きや交渉においても、過去の判例や経験に照らした力強いサポートが可能です。
-
試用期間を含めた従業員との労働トラブルは弁護士に相談を
労働トラブルが発生した場合、従業員や雇用者は早めに弁護士に相談することが重要です。労働問題に詳しい弁護士法人ブレイスは法的な知識と経験を活かし、納得感のある解決を目指します。また、トラブルの発生を未然に防ぐためにも、雇用契約や試用期間に関する法的なアドバイスが不可欠です。
労働問題に関するご相談やご質問があれば、弁護士法人ブレイスにお気軽にお問い合わせください。