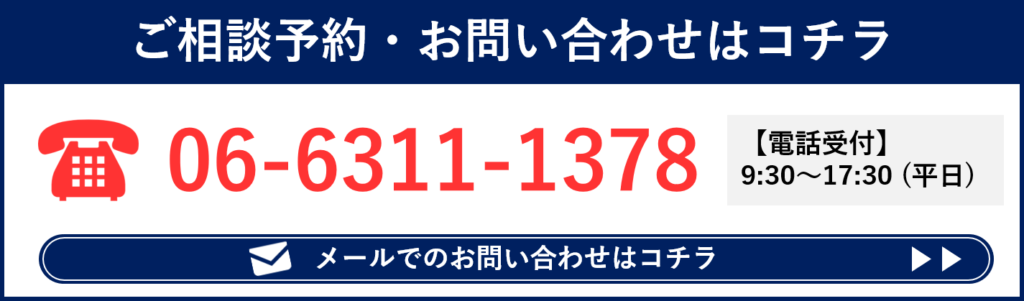近年、上司や経営者が部下から精神的苦痛を受ける「逆ハラスメント」が増加しています。
パワハラ対策が進む一方で、正当な注意や指導に対しても「それはハラスメントだ」と反発する社員が存在し、適切な指導すら困難な状況に陥っている企業が少なくありません。とくに人事部門が整備されていない中小企業では、対応を誤ると職場全体の士気低下や退職リスクにもつながります。
本コラムでは、逆ハラスメントの定義と事例、法的な視点、そして中小企業でも実践できる現実的な対処法と対応手順をわかりやすく解説します。
逆ハラスメントとは?定義と令和時代の典型事例
そもそも逆ハラスメントとは?
「逆ハラスメント」とは、一般に上司が部下に対して行うとされるハラスメントとは逆に、部下が上司や経営者、管理職に対して精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。「逆パワハラ」と呼ばれたりします。逆ハラスメントの一種として、ハラスメント・ハラスメント(なんでもかんでも「ハラスメント」と主張して反発するハラスメント、略して「ハラハラ」)も存在します。
パワハラやモラハラといった一般的なハラスメントが注目される中で、立場の弱いとされる部下からの攻撃が見過ごされやすいという問題点があります。正当な指導への反発や過剰な権利主張、報復的な言動が特徴です。
このような「逆ハラスメント」が発生した背景には、パワハラ対策の強化や働き方改革による人間関係の変化、さらには労働者の権利意識の高まりにより、上司の指導が「ハラスメント」と受け取られやすくなった現代の職場環境の変化があります。
令和時代によくある逆ハラスメントの具体例
具体的な行為としては、
●業務命令の無視や拒否、暴言
●人格否定的な発言
●周囲への悪意ある噂の流布
●SNS上での誹謗中傷
●上司の発言の録音・公開
などが挙げられます。
こうした行為は、上司や管理職に強いストレスを与え、業務遂行を妨げるだけでなく、職場全体の人間関係を悪化させかねません。
また、指導や注意を受けた部下が「それはパワハラです」と逆に責め立てることで、上司側が萎縮し、必要なマネジメントや指導が機能しなくなるケースも見受けられます。
逆ハラスメントに関する裁判例と法的なポイント
過去の裁判で「逆ハラスメント」が認定された事例
ケース1:部下の常習的暴言がパワハラと認定された裁判例
~京都地裁平成27年12月18日判決~
部下が上司(医事課長)に対して日常的に暴言を吐き、侮辱する言動を繰り返した事案。例えば、その部下は上司に「給与が高いくせに仕事ができない」と罵り、病気で手がうまく書けない上司に対して「日本語わかってはりますか」等と辛辣な発言をするなどの行為を行った。こうした常習的な暴言により上司は精神的に追い詰められ、最終的にうつ病を発症した。
裁判所は、部下による一連の言動が上司に対し強い心理的負荷を与えたと認定した。具体的には、「部下とのトラブル」による精神的ストレスが労働災害の原因の一つとなったと判断し、労働基準監督署による労災不支給処分を取り消している。つまり、部下の暴言による上司への嫌がらせ行為が法的にパワハラ(業務起因の心理的負荷)と認定され、上司のうつ病発症との因果関係が認めら、上司側の労災請求が認められることになった。
ケース2:部下の業務命令拒否がハラスメントとされた裁判例
~東京地裁平成22年11月26日判決〔アクティス事件〕~
部下が、上司の指示した業務命令に対し感情的に反発し繰り返し拒否した事案。当該部下は自分に対するセクハラ問題の対応に不満を持っており、上司や部下、同僚等に対しておびただしい数の電子メールを送信し、暴言を吐くなどの行為に及んでいた。そのため、上司や同僚、部下との関係は、もはや回復不可能なまでに根本から失われた。
会社は当該部下に対し再三指導と改善の機会を与えたが、関係修復は困難と判断し、最終的に退職勧奨の後に普通解雇とした。
部下は解雇無効を訴えたが、普通解雇は相当で有効と判断した。つまり、部下による業務命令の度重なる拒否や暴言は違法なハラスメント行為であり、その深刻さゆえに解雇という厳しい措置も正当とされたと考えられる。
法的に「懲戒処分」が可能になるラインとは?
逆ハラスメントを理由に懲戒処分を行うには、その行為が就業規則で定められた懲戒事由に該当し、弁明の機会を与えるなど適正な手続きが必要です。
懲戒処分が認められるためには、問題行動が企業秩序を著しく乱し、注意・指導にもかかわらず改善が見込めないことが重要です。加えて、処分を裏付けるための証拠として、面談記録、業務指示の文書、メールのやり取り、目撃者の証言などを時系列で整えておくことが求められます。
感情的な判断を避け、客観的な資料に基づいた対応が法的リスクを最小限に抑える鍵となります。
実録!ある中小企業での逆ハラスメント事例と対応の全体像
【発端】部下の反抗的な態度に悩む経営者
大阪府の従業員100名の健康食品販売業。上司であるA氏は、若手社員B氏に業務指導をするたびに「それはパワハラですよ」と遮られるようになった。B氏は社内のグループチャットでも上司の注意に対し皮肉交じりの返信を繰り返し、徐々に他の従業員にも悪影響が波及した。
新人が萎縮したり、ベテラン社員が「関わりたくない」と距離を取るなど、組織の空気が目に見えて悪化していった。次第に事務局長のA氏も疲弊してしまい、夜は眠れず心療内科に通院することとなった。
【第1段階】問題を把握し、記録を始める
社長は事態の深刻さを受け、社外の社労士に初めて相談した。
アドバイスを受けながら、B氏との会話メモ、社内チャットのやり取り、注意指導の履歴を記録しはじめた。特に「それハラスメントですよ」という発言が繰り返される場面や、業務命令を拒否する態度が示す場面では、逐次メモを詳細にとって、記録を保存した。
【第2段階】初期対応と注意指導
一定の記録が集まった時点で、まずは個別面談を実施した。
B氏に対し「指導を萎縮させる発言が他の従業員に与える影響」について説明し、口頭での注意を行った。この面談では、上司であるA氏だけでなく役員も同席して、A氏の負担を軽減する配慮もした。
さらに、全社員向けに社内ルールや就業規則の再確認を行い、「指導とハラスメントの違い」についても説明を行った。
注意後もB氏の態度は改善せず、面談は1か月に1回程度繰り返された。この段階ではあえて懲戒処分は下さず厳重注意書を作成し、本人に提示した。厳重注意書には「改善がない場合は懲戒処分を下す」旨の警告も加えた。
【第3段階】逆ハラスメントが改善しない場合の対応
警告後もB氏の態度は改善せず、業務命令の無視やチャット上での挑発的な発言が続いた。社内に懲戒委員会はないため、A氏は顧問社労士経由で弁護士に相談した。
弁護士の助言により、懲戒処分に向けた手順(懲戒事由該当性の整理、弁明の機会付与通知書の作成)を進め、面談にも弁護士が同席した。懲戒処分は減給処分とした。
結果的にB氏は懲戒処分に耐え切れず自主退職を選択して、職場環境の正常化につながった。
逆ハラスメントへの対応手順のまとめ
☑ 事実関係の整理と証拠の保全
問題社員の言動について、日時・内容・関係者を含めた客観的な記録を残します。録音・メモ・メール・チャット履歴などが有効です。
☑ 書面による注意・指導・警告
注意や警告は、口頭にとどまらず書面で行いましょう。厳重注意書などの書面には、「改善がない場合は懲戒処分を下す」旨の警告を加えることも有効です。
☑ 面談記録・業務日報などの管理
改善を求める面談は定期的(1か月に1回など)に実施し、面談時の指導内容や問題行動への企業の対応を面談記録などで文書化し、継続的な記録として保管しましょう。人事評価や配置転換時にも役立ちます。
☑ 継続する場合は外部の専門家(弁護士や社労士)へ相談
行動が改善せず懲戒処分やその対応に不安がある場合は、早めに労働問題に詳しい弁護士や社労士に相談し、懲戒処分への道筋の助言を受けることがお勧めです。
自社対応で限界を感じたら早期に弁護士へ相談を!
逆ハラスメントは「指導しづらい部下だから」と見過ごしていると、職場の秩序が崩れ、他の社員にも悪影響を及ぼします。放置すれば上司や管理職が萎縮し、組織全体の士気低下や優秀な人材の離職を招く可能性もあります。
問題が深刻化する前に、早めに弁護士へ相談することが重要です。弁護士は、懲戒処分や退職勧奨が法的に有効な慎重に吟味し、記録・証拠の整備や対応手順の整理を支援してくれるため、企業も安心して的確な判断ができるようになります。
ただし、弁護士の選ぶ際には、ハラスメント問題を含めて労働問題に詳しい弁護士であるかどうか、慎重に吟味する必要があります。
ハラスメント問題に関する相談・アドバイス
当事務所は、ハラスメント問題を含めて労働問題に詳しい弁護士が所属しており、過去の経験やノウハウ、これまで蓄積された判例などの知識により、ハラスメント防止措置義務に則った適切なアドバイスができます。
ハラスメントの申告があれば、調査の仕方、被害者への対応や加害者への処分の可否・程度など、初動対応全般をアドバイスします。また、問題が解決した後もハラスメント予防策として就業規則の整備、管理職への指導教育方法、社内研修の実施なども提案いたします。
従業員間におけるハラスメントトラブルへの対応
従業員間でハラスメントのトラブルが発生した場合、最終的に企業がハラスメントの有無を正しく認定する必要がありますので、その前提となる社内調査が極めて重要となります。社内調査がずさんで認定を誤れば、その後の対応方法もすべて不適切なものとなるからです。
当事務所は、ハラスメント問題について多数取り扱ってきた経験やノウハウに基づき、ハラスメントの実態を把握するための社内調査を支援し、適切な証拠収集方法を指導します。関係者の誰にどのような内容を聴けばよいのか方針を示し、メールやメッセージの記録、目撃証言、映像などの証拠を整理・分析し、企業様がハラスメントの有無を正しく判断できるように支援いたします。
ハラスメント問題の防止に向けた社内向け研修
当事務所の代表弁護士はこれまで、社会保険労務士会、税理士会等での研修講師や、商工会議所や出版社主催のセミナー講師、クライアントの社内研修など、数多くや研修等に登壇してきた実績を有しております。
パワハラ研修も数多くこなしており、パワハラ防止措置義務の概要、パワハラの具体例、パワハラと正当な指導教育との境界線などを、自らの経験や実績に基づき分かりやすく解説することができます。これまで数多くの参加者(社労士や税理士を含む)の方々から、「具体的で分かりやすく理解が進んだ」「パワハラと正当な指導教育との境界線が分かり、自信をもって指導教育ができそうだ」などの声をいただいております。
経験と実績に裏付けされた社内向け研修により、ハラスメント防止のための従業員教育が実現し、職場全体の意識向上に繋がることは間違いありません。ハラスメント関連法の最新情報や法改正に関する情報も提供し、企業様のハラスメント対応をサポートします。このようなパワハラ研修の開催実績それ自体が、会社がパワハラ防止措置の義務を尽くしていることを示す事情となります。
是非とも、当事務所のパワハラ研修をお試しください。
顧問契約によるトラブル防止に向けた体制構築
社内でハラスメント問題が発生し、その結果被害者が企業様を訴える労使紛争に発展することがあります。労使トラブルに発展する企業様は、そもそも、その企業様の労務管理において根本的な問題やリスクが潜んでいる可能性があります。そうなると、労使紛争を解決しても、その解決は対症療法に過ぎず、根本治療がなされないまま、再度同様の労使紛争が発生することがあります。そのような労使紛争を繰り返す企業様も実例として見てきました。
当事務所では、顧問契約や労務コンサルティングにより、労務管理における根本的な問題やリスクを解消することができます。このような根本治療により問題を根本的に解決できれば、労使紛争は激減し、かえって労使紛争により生じる費用が節約されコストカットになりますし、何よりも企業様が望むハラスメントのない快適な職場環境の構築には不可欠です。
同じ労働問題に対して、事前法務・日常管理的な業務を行う社労士と、事後法務・危機対応的な業務を行う弁護士とで、事案の捉え方や解決の視点が異なることがあります。また、ある法改正でも、社労士と弁護士とで視点が異なるため、法改正情報の着眼点や重視するポイントが異なります。時として、顧問弁護士と顧問社労士の見解が異なり、どちらの見解に従えばよいか混乱している企業様もいます。
当事務所は、顧問契約や労務コンサルティングにおいても、弁護士・社労士の両視点を統合した最適解や重要情報を提示しております。
ハラスメント問題に関するご相談は労務問題に精通した弁護士と社労士が在席している当事務所にお任せ下さい。